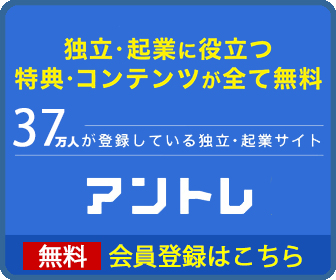個人事業主は原則労災保険に加入できないため、加入していない方も多いのではないでしょうか。
しかし、個人事業主でも加入しなければいけない場合や特別加入ができる場合があるのはご存じですか?
本記事では、労災保険に加入していない場合のペナルティやデメリット、リスクについて解説しています。
個人事業主自身が労災保険の対象になれる事業についても説明しているので、ぜひ最後までご覧ください。
個人事業主が労災保険に加入するための条件

繰り返しになりますが、個人事業主は労災保険に加入できません。
なぜなら、労災保険は「雇用されている労働者」の業務中や通勤時のケガ・病気・障害・死亡の場合に労働者や遺族に保険給付される制度だからです。
そのため、雇用されている労働者ではない個人事業主は、労災保険の対象になりません。
しかし、下記の加入条件に該当すれば加入が可能です。
1つずつ解説します。
従業員を雇用している
事業形態や職種に関わらず1人でも従業員を雇用すると、事業主として労災保険への加入が義務付けられます。
従業員の雇用形態は正規雇用に限らず、パート・アルバイトでもすべて加入対象です。
加入義務を怠ると罰則もあるため、従業員を雇用した場合は10日以内に労働基準監督署で加入手続きをしましょう。
ただし、この場合の労災保険の対象者は従業員のため、個人事業主自身は対象外です。
したがって、個人事業主の場合、労災保険の代わりに民間の保険に加入するなどの対策をする必要があります。
特別加入制度の対象になっている
個人事業主は、基本的に労災保険の対象にならないと記載しました。
しかし個人事業主のなかには労働者と同じ業務をおこなっており、その業務の内容や災害発生の可能性から、労働者と同様に保護することがふさわしい場合があります。
その場合、特別加入制度として一定条件のもと労災保険に任意加入し、補償を受けることができます。
特別加入制度を利用し労災保険に加入できる対象は、大きく分けて以下の4種の事業をおこなう場合です。
| 中小事業主など | 1人以上の労働者を100日以上雇用し、労働者と同じ業務に従事している人。 |
| 一人親方 | 労働者を使用せずに、一定の事業をおこなう人。 個人タクシーや個人貨物運送業者、大工、あん摩マッサージ指圧師、歯科技工士など。 |
| 特定作業従事者 | 特定農作業従事者・指定農業機械作業従事者・国または地方公共団体が実施する訓練従事者・労働組合等の一人専従役員・家内労働者およびその補助者・介護作業従事者および家事支援従事者・芸能関係作業従事者・アニメーション制作作業従事者・ITフリーランスなど |
| 海外派遣者 | 日本国内の事業主や国際協力機構など、海外でおこなわれる事業に労働者もしくは事業主(労働者ではない立場)として派遣される人。 すでに海外事業に派遣されている場合も加入できるが、現地採用の場合は対象外。 |
特別加入できれば、通常の労災保険と同じように、万が一のときの保障につながるでしょう。
従業員がいる個人事業主が労災保険に加入していない場合のペナルティ

従業員を1人でも雇用している個人事業主は、必ず労災保険に加入しなければなりません。
従業員がいるにも関わらず、労災保険に加入していなければ、法律違反による罰則があります。
この3つの状況で、労災保険未加入の場合にどのようなペナルティがあるのかを説明します。
従業員が事故を起こした場合
労災保険に加入していなくても、業務中に事故が起きた場合には労災保険が適用されます。
従業員を雇用すると労災保険への加入が義務のため、未加入でも労働者は保護されます。
「それなら業務中の事故が起こった場合に加入すればいいじゃないか」と思う方もいらっしゃるかもしれません。
しかし未加入で事故が起きた場合、事業主は過去2年間をさかのぼった未払い保険料に加え、10%の追徴金の支払いが課せられます。
これに加え、故意や重大な過失に当てはまる場合には、労災保険給付額の全部または一部が徴収されます。(故意と重大な過失の場合は、次の項目で解説)
そのため、事故が起こってしまったあとだと、多額の支払いが必要になる可能性があります。
したがって、従業員を雇用した時点で、労災保険に加入したほうがいいでしょう。
故意に加入手続きをしなかった場合
故意に労災保険に加入手続きをしなかった場合とは、労働局職員や労働基準監督署の監査官から加入手続きをおこなうよう指導されていたにも関わらず、労災保険に加入していない場合です。
この場合、事業主の故意による未加入とみなされ、未払保険料と追徴金に加え、労災保険の給付額全額が費用徴収されます。
重大な過失と判断された場合
重大な過失と判断されるのは、労働局職員などから加入手続きの指導はされていないが、従業員を雇い労災保険に加入すべき状況になったにも関わらず、1年間以上労災保険に未加入の場合です。
この場合に事故が起きると、事業主の重大な過失として未払保険料と追徴金に加え、保険給付額の40%が費用徴収されます。
個人事業主自身が労災保険に加入していない場合に起こるデメリット

個人事業主自身が特別加入制度の対象で労災保険に加入できる状況にも関わらず、未加入の場合、以下の2つのデメリットが考えられます。
1つずつ説明します。
案件を受注しづらい
特に建設業をおこなう一人親方は、案件が受注しづらくなります。
それは、案件発注の際に「労災保険に加入していること」を条件としている企業が多いためです。
もし労災保険に加入していない一人親方に発注し、業務中にケガをしてしまった場合、発注元の企業の管理責任が問われることがあります。
このような事態を避けるため、発注元の企業が労災保険の加入を仕事の発注の際の条件に入れている場合が多いです。
そのため、労災保険に加入していなければ案件を受注しづらくなるでしょう。
業務中に起きた事故の補償を受けられない
もし労災保険に加入していなければ、業務中に事故が起きてケガなどをした場合の補償を受けることができません。
補償がないので、医療費などの費用を自分で負担しなければいけないことはもちろんですが、仕事を長期間休まなければならない場合、収入がなくなってしまう可能性があります。
これは、個人事業主にとって死活問題です。
労災保険に加入していれば、働けなくなってしまった場合も休業4日目から給付金が支給されます。
また、万が一の場合には遺族に対して給付金が払われるため、事故後の自分の生活や家族の生活が保障されるので、資金面でのリスク軽減につながります。
ただし、労災保険はさかのぼって加入ができないため、注意してください。
まとめ

- 1人でも従業員を雇用していると、労災保険の加入が必須になる
- 特別加入制度で個人事業主自身も労災保険の対象になれる
- 従業員を雇用していて、労災保険に未加入の場合に事故が起こると徴収される金額が多額になる可能性がある
- 労災保険に未加入の場合、案件が受注しづらくなる
- 労災保険はさかのぼって加入ができない
個人事業主は会社員に比べ、ケガや病気になった場合のリスクが高いです。
労災保険に加入していれば、万が一業務中に災害が起こってしまっても国からの手厚い補償を受けられます。
業種によっては案件を受注しにくくなる場合もあるため、もし特別加入できる業種で事業をおこなっている場合、労災保険への加入をおすすめします。